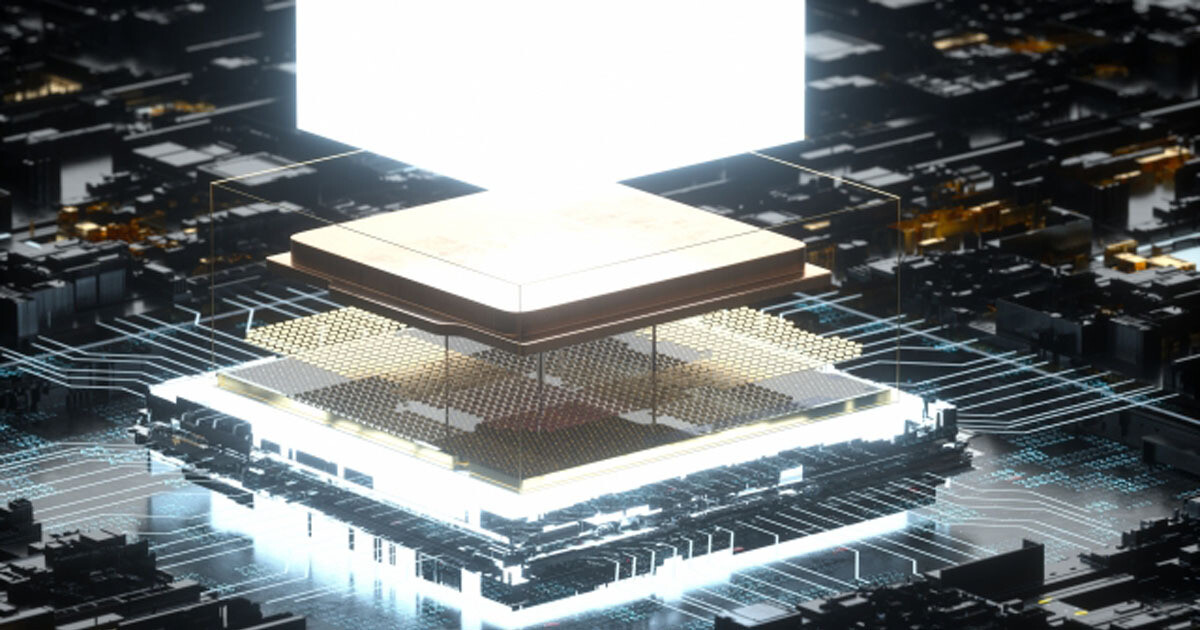日本の3Dパッケージング技術は世界の基準になれるか? - SHARP Tech-Forum
2023年08月08日16時20分 / 提供:マイナビニュース![]()
●阪大 産業科学研究所の菅沼克昭名誉教授が講演
2023年11月11日、シャープは創業111周年を記念し「Sharp Technology Day」を開催する。同イベントでは、シャープの今後の技術戦略を紹介するとともに、独自技術を採用した製品・ソリューションを展示する予定だという。
そして同社は、社内のさまざまなテクノロジーを集結させる一大イベントの開催に先立ち、8月7日には先行イベントとして「SHARP Tech-Forum」を開催。昨今産業界全体として大きな関心を集める“半導体”をテーマに据え、産官学それぞれから専門家が登壇し、技術の動向や日本の戦略、将来への展望について講演を行った。
学術機関の視点から3Dパッケージング技術を展望
大阪大学 産業科学研究所の名誉教授で、同研究所 フレキシブル3D実装協働研究所長も務める菅沼克昭名誉教授による講演では、「協働で拓く次世代半導体実装技術」と題し、半導体の3Dパッケージング技術における世界の潮流と、日本が目指すべき技術の方向性について語られた。
微細化限界の到来で重要性が高まる3Dパッケージング技術
半導体プロセスの微細化には、限界が迫っている。現在開発が進められる最先端プロセスは2nmまで微細化されており、これは原子のサイズを鑑みると、微細化の物理的限界に近付いているとされる。
そこで次なる流れとして、半導体チップを組み合わせることで高密度高性能を実現するチップレット化に注目が集まっている。そして、その性能向上において大きな重要性を持つのが、3Dパッケージング技術だ。
Appleが開発した最新のCPU「M1 Max Ultra」でもその実装技術が用いられており、2個のCPUや8個のメモリ、GPUなどが1つのチップレットに搭載されている。その結果、大幅な高速化や歩留まり向上といったメリットに加え、同等の性能で比較した場合の消費電力低減でも大きな効果を発揮しており、今後もこうした形での技術革新が進んでいくのは明らかだとする。
米国政府も半導体パッケージング技術を重視する姿勢を強めており、全米先端パッケージング製造プログラム(NAPMP)に対して25億ドル規模の投資が行われている。これは、CHIPS法で推進される半導体研究開発プログラムの中核を担うとされる国立半導体技術センター(NSTC)への投資(約20億ドル)よりも大きい規模であり、菅沼名誉教授は「米国としてパッケージングの技術や材料が不足しており、国内で半導体のエコシステムを作るために、パッケージングに注力していく必要があるという方向性が見える」と説明する。
●国際標準として日本技術の信頼性が求められる可能性も
高信頼性を誇る日本の技術は業界の基準になりうる
需要が一気に高まる3Dパッケージング技術について、日本国内の半導体メーカー各社は、それぞれの製品開発の中でさまざまな技術開発を進めてきており、その技術は世界でも存在感を発揮するという。
チップレット化において重要な技術としては、複数の半導体と基板をつなぐ際に、中継部材のインターポーザ―を使わずにチップ同士を接続する「ブリッジ構造」や「再配線層(RDL)」などが挙げられる。電気特性の改善につながるこうした接続技術は、各メーカーが独自に開発・実用化を進めているため、激しい競争によって性能向上が進んでいるとする。
ハイブリッド接合やサブストレートの微細化など、さまざまな技術を組み合わせるチップレット化に向けては、技術と材料の両面で進歩を遂げている日本の優位性があると菅沼教授は語る。実際に、先般開催されたG7に際して、岸田文雄首相と世界の大手半導体企業トップとの間で意見交換が行われた際には、Intelをはじめとする各企業が、パッケージングなどの後工程に関する拠点の日本への設置を検討する姿勢を見せるなど、国際的な注目を集めている。
また、日本の半導体技術が注目される背景には、信頼性に対する要求の高まりもあるとのことだ。近年の半導体需要拡大は、AIと並んで自動運転の普及が牽引しており、社会インフラにおける需要も高まっている。人命や社会活動に関わるこれらの領域で使用される半導体に対しては、性能と同時に信頼性の高さも必ず求められる。性能向上を目指す上で切り離せない熱効率の改善なども信頼性に大きく影響するため、これらを向上させる3Dパッケージング技術の開発が必要とされる。菅沼名誉教授は、「高信頼性と高機能の両立は、もとより日本が強みとしている部分」と語り、日本の製品が世界標準になる可能性も十分に考えられるとしている。
チップレット技術の普及や低コスト化に向けた国際的なオープン規格として「UCIe」が立ち上がるなど、チップレット技術においては国際標準化が進んでいる。「世界のスタンダードを決めていく中で、日本がその流れに寄与していくことが望ましい」と菅沼名誉教授が語るように、発展途上のチップレット化において日本の技術がどれほどの存在感を放つことができるかが、今後の半導体開発競争に大きく影響していくと考えられる。
産学連携による人材の育成・確保が重要
学術機関に所属する菅沼名誉教授は、講演の最後に、台湾における半導体産業を支える高等教育体制を例示しながら、半導体産業の人材体制に言及した。
半導体産業が盛んな台湾では、TSMCやASEなどの半導体企業の拠点と、トップ4大学が、非常に近い場所に位置しているという。またこれらの大学では、法整備により2022年から半導体学科が設置されているとのことで、国家をあげて半導体産業に注力している姿勢が見られる。
台湾を視察した際には「学生たちの目がキラキラしていて、非常にうらやましい環境だった」といい、産業と学術機関が連携しやすい体制づくりの重要性を強調したうえで、「人材が育つ場所でこそ企業が育つ。こういった環境づくりを日本でも行っていきたい」と今後の展望を語った。
関連記事
- 半導体の高性能化はチップレットが担う時代へ、SHARP Tech-Forum
- 日米政府がTSMCの先進パッケージング工場を自国に誘致を画策か? 台湾メディア報道
- TSMCがCoWoS向け新工場建設用地を新竹科学園区に確保か? 台湾メディア報道
- 先進パッケージング市場は年率40%で成長し2028年に160億ドル規模に、Yole予測
- TSMC、3D実装に対応した先進後工程工場を台湾・竹南サイエンスパークに開設